| CD |
レーベル,規格番号及びコメント |
音質
評価 |
.JPG) |
- ISLANDPROS RX3201(Theory盤)
- 英EMIのSP(DB 21131/3)からの復刻。
- CD−R盤。
- TDKの音楽専用CD−R“THEORY”を使用。
- 高音質化のため,記録する線速度をCDの規格の最長である1.4m/秒としている。
- 編集で音を継いでおらず,SP盤の面が終わる度に音が中断する。
- ノイズカットは行っていないので,スクラッチノイズは盛大に聴こえる。
- 盛大なスクラッチノイズの中から聴こえるウィーンフィルの響きの質感や実在感に優れており,聴感のレンジも広い。
- フォルテで音がキツくなったり,潰れたりすることもない。
- エレガントで充実したオケの響きと,しなやかなロマンティズムに溢れる演奏の姿を再現しているという点では他のCDを圧倒しており,当盤で聴くと,この演奏がいかに充実した名演であるかが実感できる。
- 明るくカラッとした音質が耳に心地良く,柔らかみのある美しいソノリティを聴くことができるが,これはTHEORY盤の音の特色かもしれない。
- SPの面が変わる度に音が途切れることや,スクラッチノイズが盛大なことについては音質評価に当たって考慮していない。
|
95 |
 |
- ISLANDPROS (規格番号無し)(Green Tune盤)
- 英EMIのSP(DB 21131/3)からの復刻。
- CD−R盤。
- 三菱化学メディアのの音楽専用CD−R“Green Tune”を使用。
- 高音質化のため,記録する線速度をCDの規格の最長である1.4m/秒としている。
- 編集で音を継いでおらず,SP盤の面が終わる度に音が中断する。
- ノイズカットは行っていないので,スクラッチノイズは盛大に聴こえる。
- 盛大なスクラッチノイズの中から聴こえるウィーンフィルの響きの質感や実在感に優れており,聴感のレンジも広い。
- フォルテで音がキツくなったり,潰れたりすることもない。
- 充実した存在感のあるオケの響きと,引き締まったロマンティズムに溢れる演奏の姿を再現している。
- THEORY盤よりもさらに深みと実在感のある音質であり,マスターの音質により近づいている印象。
- THEORY盤のようなソノリティの美しさとは異なった,ハイフィデリティに徹した中にも味わいのある音質であるが,やや湿ったような印象の音質となっている。
- SPの面が変わる度に音が途切れることや,スクラッチノイズが盛大なことについては音質評価に当たって考慮していない。
- THEORY盤よりもややシリアスな演奏に聴こえる。
- Theory盤とGreen Tune盤はそれぞれ甲乙付けがたいが,仏盤の音質が好みであればTheory盤,独盤の音質が好みであればGreen
Tune盤がよいと思われる。
- 当盤には2種類の復刻が収録されている。1つはSP復刻の音質をそのまま記録したもので,もう1つは若干のノイズカットを行ったもの。当欄の音質評価はそのまま復刻した方である。ノイズカットした方の音質は若干ニュアンスの乏しい無機的な音となるため評価は低くなる。
|
95 |
.JPG) |
- ISLANDPROS RX3201(Normal盤)
- 英EMIのSP(DB 21131/3)からの復刻。
- CD−R盤。
- 高音質化のため,記録する線速度をCDの規格の最長である1.4m/秒としている。
- 上記THEORY盤と同一マスターだがCD−Rメディアが異なる。
- 音質は上記THEORY盤に準じることになるが,響きのニュアンスは多少無機的であり,やや細身で冷たい印象の音質でTHEORY盤のようなソノリティの美しさは聴かれない。
- SPの面が変わる度に音が途切れることや,スクラッチノイズが盛大なことについては音質評価に当たって考慮していない。
- 当方が所持している盤は,CD−Rドライブの電源にオキシライド乾電池16本を使用している。
|
92 |
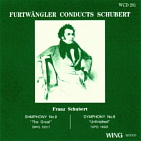 |
- 仏VSM(HMV)のLP(FALP 317)からの復刻(LPマスター2)。
- (LPマスター2)独自の混入ノイズが聴こえるほか,第1楽章の最後2分弱くらいで,元のLPに起因していると思われる周期的な音の途切れがある。
- スクラッチノイズのレベルは低く気にならない。
- 比較的穏当な音質で,再生しやすく聴きやすい。
- LP復刻としては良好な音質だが,それでも音の情報量がいまひとつといった感は否めない。
- 響きの質感は比較的良い。
- ノイズの混入や周期的な音の途切れれがあることについては音質評価に当たっては考慮していない。
|
90 |
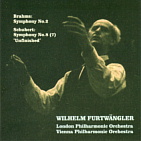 |
- 英EMIのSP(DB 21131/3)からの復刻。
- SPのスクラッチノイズはカットしていないようだが,そのレベルは並程度。
- 低域を持ち上げ,高域を下げた音域バランス。
- 低域のフォルテがボン付く。
- 音の情報量としてはSP復刻のメリットはあまり感じず,条件の良いLP復刻やCD並み。
|
90 |
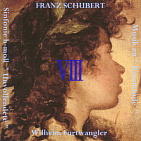 |
- 米MYTHOS NR-5023PRO(Green Tune盤)
- 独エレクトローラのLP(WALP 1500)のテストプレス盤からの復刻(LPマスター1)。
- CD−R盤。
- 米MYTHOS盤のマスターグレードというシリーズで,,三菱化学メディアの音楽専用CD−R“Green Tune”を使用。
- 同じマスターのTHEORY盤と比較すると,より落ち着きのある音質で演奏を聴くことができる。
- 音色や響きはやや湿った感じだが,こちらの方が元のLPの音質に近いのかもしれない。。
- 米MYTHOS盤の大袈裟な音質がいくぶん緩和されているように聴こえる。
|
90 |
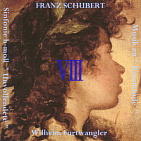 |
- 米MYTHOS NR-5023PRO(Theory盤)
- 独エレクトローラのLP(WALP 1500)のテストプレス盤からの復刻(LPマスター1)。
- CD−R盤。
- 米MYTHOS盤のマスターグレードというシリーズで,TDKの音楽専用CD−R“THEORY”を使用。
- LPのスクラッチノイズはやや多め。
- 復刻に用いたLP自体の音のせいか,響きや音色の質感も良いが,SP盤ほどの確かな音のニュアンスは聴かれない。
- 力感と存在感のあるドラマチックな聴き映えのする音質。
- スケール感もあるが,ややデフォルメされた印象の音質。
- エネルギー感優先の音質のため,やや騒々しく感じる。
- 音の充実度としては驚嘆すべきものがあるが,演奏の姿を誤り無く再現するというより,音盤製作者の自己主張の優った印象の音質。
|
89 |
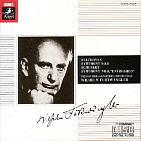 |
- 東芝EMI CC35-3162
- 東芝EMI CE28-5574
- 英EMIがCD用に初めてマスタリングしたもの(CDマスター1)。
- CC35-3162はこの録音の世界初CD。
- CD28-5574は再発売盤。
- マトリックスは2DJ-3046-7-CDだが,CDC 7 47120 2 が併記されているプレスもある。
- 音の鮮度はいまひとつで,いくぶん解像度の甘い音質だが,バランスが良く聴きやすい。
- 響きや音色の質感は比較的良いが薄目で,力感もそれほどではない。
- デジタルマスタリングによって音が無機的になることがなく,響きや楽器のニュアンスもある程度保たれている。
|
88 |
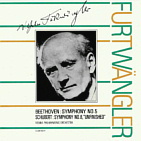 |
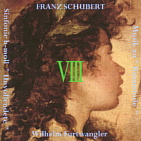 |
- 独エレクトローラのLP(WALP 1500)のテストプレス盤からの復刻(LPマスター1)。
- CD−R盤。
- 米MYTHOSのゴールドCD仕様で,Mitsui Inkjet の金反射膜CD−Rを使用。
- LPのスクラッチノイズはやや多め。
- THEORY盤と比較すると響きがやや平板で金属的であり,リアルな音の存在感や音場感といった点でも遜色があるが,大袈裟な音ではなく聴きやすいともいえる。
- 独自の音の艶があって聴き映えがする。
|
87 |
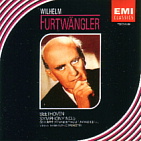 |
- 東芝EMIが1994年にリマスターテープ使用として発売したもの(CDマスター2)。
- マトリックスは2DJ-4684
- (CDマスター2)であるが,同マスターの他の盤盤よりもノイズが目立つ。
- しっかりとした存在感のある音で,音の粒立ちも比較的良好。
- 今のところ(CDマスター2)のCDの中では最も音がよいが,条件の良い(CDマスター1)よりも情報量に遜色があり,ややニュアンスにも乏しい。
|
86 |
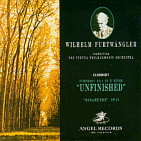 |
- 東芝EMI GSD-6711
- 東芝EMI TOCE-11011
- 東芝EMI TOCE-3748
- HS−2088マスタリング(CDマスター1)。
- マトリックスは2DJ-5524-HS
- リマスタリングエンジニアは Yoshio Okazaki と記載されている。
- 音質はCC35-3162と比較すると,やや硬質でくっきりとした音になっている。
- 反面,音の軽さや伸びやかさはやや後退気味である。
|
85 |
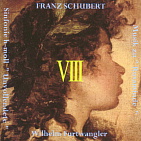 |
- 米MYTHOS NR-5023
- 独エレクトローラのLP(WALP 1500)のテストプレス盤からの復刻(LPマスター1)。
- CD−R盤。
- 米MYTHOSのノーマル仕様。
- LPのスクラッチノイズはやや多め。
- オケの響きやが上手く再現されており,抜けも良いが,THEORY盤やGold盤ような際立った音の特長はない。
- 再生音としてはやや平凡かもしれないが,音にくどさがなく,むしろ聴きやすいともいえる。
|
85 |
 |
- EMI CLASSICS BEST 100 での発売(CDマスター2)。
- マトリックス番号の表示は無し。
- リマスタリングエンジニアは Yoshio Okazaki と記載されている。
- ノイズレベルが低く聴きやすいが,TOCE-8439の音源にノイズカットを施したような音質。
- 響きが薄く,微小レベルの情報がカットされているような印象。
|
84 |
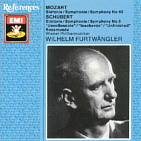 |
- 英EMIによる1984年のデジタルマスタリング盤(CDマスター1)。
- 1980年代から90年代にかけて広く世界中でリリースされていたCD。
- 音色や響きのニュアンスはある程度保たれている。
- ややスケール感に乏しく,音像も小さめ。
- あまり聴き映えはしないが,作為的な感じの少ないマスタリング。
|
82 |
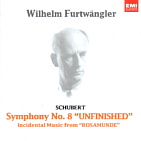 |
- 東芝EMIによる2004年の24ビットリマスタリング盤(CDマスター1)。
- マトリックス番号の表示は無し。
- フォルテで高域がキツく歪むことがあるのが多少気になる。
- 厚みのあるしっかりした音質で聴き応えがある。
- デジタルマスタリングによってやや無機的な音調になっており,音色や響きのニュアンスは失われがちである。
|
80 |
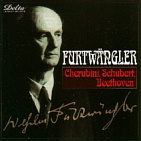 |
- 英EMIのSP(おそらく DB 21131/3)からの復刻。
- スクラッチノイズはカットしていないとのことだが,パチパチという針音をシャーというノイズに変換しており,デジタルマスタリングは行われているようである。
- 低域がややボン付く。
- 楽器のソロは繊細な感じが出ているが,線が細く無機的。
- 音の力感や存在感はあるが,響きとしては暗黒系の音質。
|
78 |
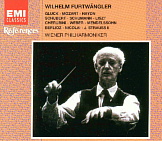 |
- 英EMIによる1998年のARTマスタリング盤(CDマスター2)。
- 爽やかで抜けのよい音質。
- オケの響きの質感は洗い落とされてしまったような印象。
- シリアスな雰囲気の音に上手くまとめている。
- ややおとなしい印象の音質となっている。
- この盤の初回プレス盤は第2楽章の冒頭4分強が欠落しているが,再プレス盤では修正されている。判別方法は,ケース裏に表示されているこの作品の演奏時間が23分56秒となっているものが正常盤である。
|
76 |
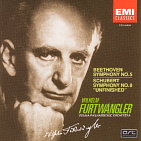 |
- ARTマスタリングの国内盤(CDマスター2)。
- マトリックス番号の表示は無し。
- 癖や違和感のないバランスの良い再生音。
- すっきりした解像度の良い音。
- 響きの厚みは多少感じるが,やや素っ気ない
- ややおとなしい印象の音質となっている。
- 音の情報量はやや物足りない。
|
75 |
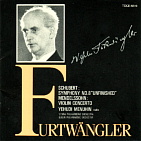 |
- ステレオプレゼンスを加えたブライトクランク盤(CDマスター2)。
- マトリックスは2DJ-3777
- ヒスノイズも含めて音が左右に広がって聴こえる。
- アタックがマイルドになっている。
- 微少レベルの音がカットされており,ニュアンス不足で,音の背景が暗く感じられる。
- 音の情報量はやや物足りない。
- フォルテでシャリシャリした音になる。
|
72 |
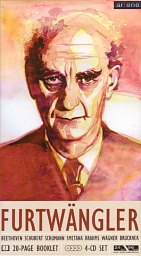 |
- 使用している音源は不明。
- 24bit/96kHzマスタリングと表示されている。
- ヒスノイズはほとんど聴こえない。
- ダイナミックレンジは確保されており,音のバランスはよい。
- デジタルマスタリングとノイズカットによって,音のニュアンスは失われてしまっており,かなり無機的な音になっている。
|
58 |
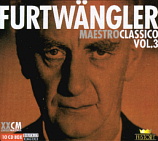 |
- 使用している音源は不明。
- 音は楽器の音色の再現すら危うく,例えばヴァイオリンの音色などは電子合成されたような無機的音にしか聴こえず,極めて情報量の少ないサンプリングを行うとこのような音になるのかもしれない。
- ダイナミックレンジは十分確保されているが,フォルテはヒステリック。
- フルトヴェングラーの演奏を鑑賞できるといったレベルの音質とはいい難い。
|
50 |
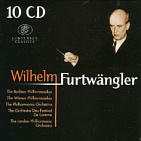 |
- 独CENTURION CLASSICS IECC 10009
- 使用している音源は不明だが,おそらくHISTORY盤と同一音源。
- 当方が所持している盤では第1楽章が冒頭の27秒しか収録されていない。
- 音質はHISTORY盤よりもさらに無機的な音質になっている。
|
48 |
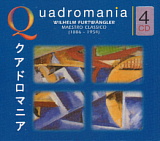 |
- 使用している音源は不明だが,おそらくHISTORY盤やCENTURION CLASSICS盤と同一音源。
- 音質はCENTURION CLASSICS盤よりもさらに無機的な音質になっており,もはや録音を聴いているという印象はなく,不気味な音の合成物を聴かされているような印象である。
|
45 |